中3になると模試の回数が一気に増えるけど本当に必要なの?
この春から息子が中3になりますが、塾から「中3は模試が年6回あります」と言われて驚いています。1年生と2年生の時は年3回だったのですが、受験生になった途端こんなに増えるものなのでしょうか? 模試代も決して安くはなく、毎回結果に一喜一憂するのも親子ともに疲れます。もちろん志望校の判定は大事ですが、模試ばかり受けて学校のテスト対策が疎かになってしまわないか不安です。そもそも6回は受けすぎだと思うのですがどう思いますか?
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス
中3になると受験校の絞り込みや学力の推移を確認するために模試の回数が増えます。特に、志望校の判定基準や出題傾向に慣れるため、一定の回数は必要です。ただし、模試の目的は「結果」だけではなく「弱点の発見と克服」です。毎回の模試後に、どの分野を重点的に復習すべきかを分析し、次の勉強に活かすことが重要です。模試の回数に疑問があるなら、塾と相談し、どの模試が必要か取捨選択するのも一案です。
 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス
親として模試代の負担や子どもの精神的な負荷は気になりますよね。確かに判定は気になりますが、大切なのは受験本番で実力を出せること。模試の回数が多すぎると、その対策に追われ、基礎学力の向上が疎かになることもあります。模試の目的を整理し、受ける意義のあるものを選び、親子で冷静に向き合うことが大切です。結果に一喜一憂せず、模試は学習のペースメーカーと考え、前向きに活用しましょう。
 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス
塾の模試受験は義務ではなく、あくまで学習の一環です。塾によっては「全員必須」と案内する場合もありますが、契約内容や塾の規約を確認し、希望に応じて調整できるか相談するのも手です。また、模試の回数が多いと精神的な負担が増すこともあるため、子ども自身の意向も尊重しながら選択するのが望ましいでしょう。模試の受験が強制でないことを理解した上で、納得のいく形で進めることが重要です。
本サービスで提供されるアドバイスや見解は、あくまで個人の意見です。これを参考にした結果生じた損害やトラブルについて、当社は責任を負いかねます。また、法的安心の視点でのアドバイスは正式な法律相談ではありません。具体的な法的問題は、専門の弁護士にご相談ください。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス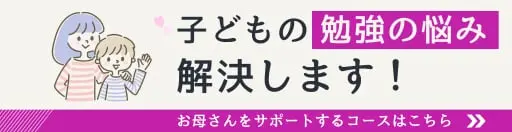
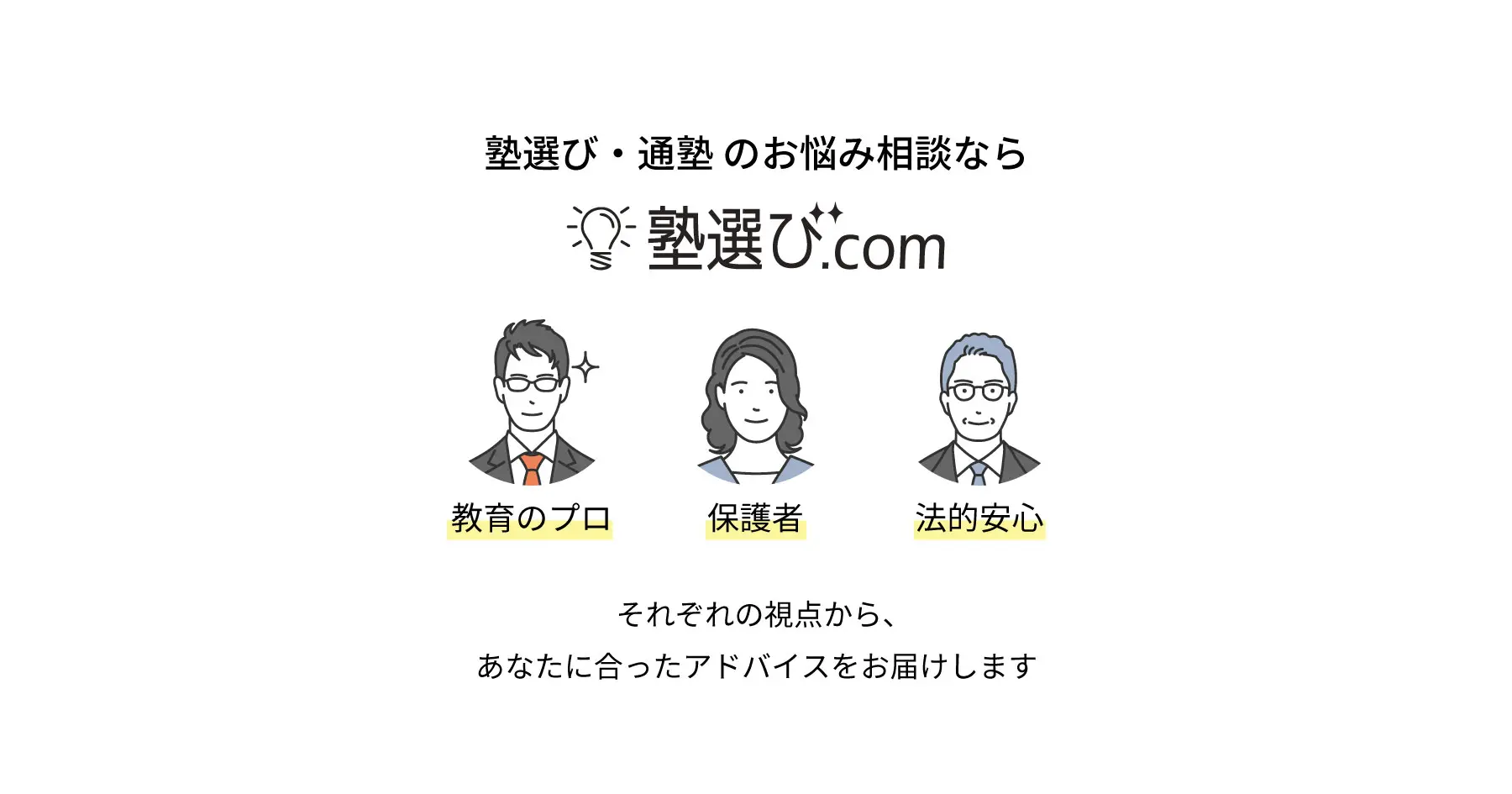


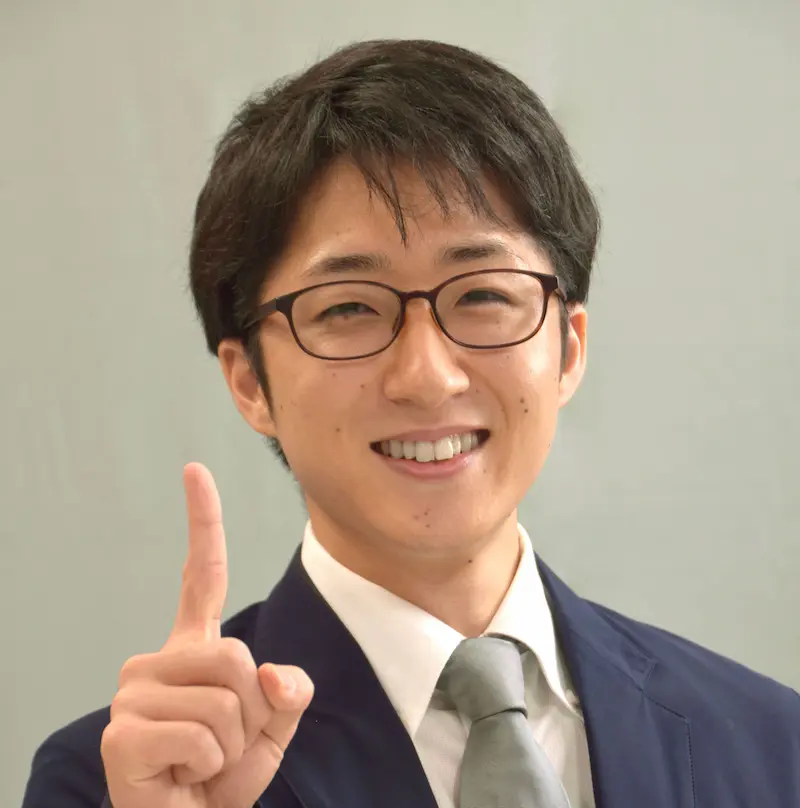






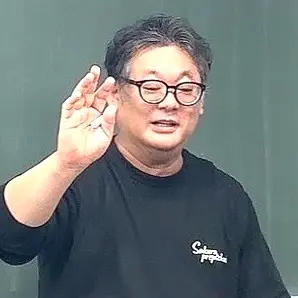



有識者の見解 (3件)
山本 力大 先生
オンライン個別指導塾Cheers!
こんにちは!
中3になると模試の回数がぐっと増える話、びっくりしますよね。
さて、まず結論からいうと、はい、増えます。
中3になると、模試の回数が一気に倍増するのは、わりと“あるある”です。特に受験を控えた学年では、定期的に「今の自分の立ち位置」を確認しておこう、という目的で、塾側も模試を組み込んでくるんですね。
でも、ここでちょっと立ち止まって考えたいんです。
「本当に6回も必要?」って。
たしかに、模試は受けた分だけ経験値になります。でも、それが全部有意義かというと、正直そうとは限らないんです。
よくあるのが、こんなパターンです。
模試を受ける → 結果を見る → 偏差値に一喜一憂する → でも復習はサッとしかやらない → 次の模試へ…
はい、これ、もったいないサイクルです。
模試は、受けることそのものよりも、「どう復習するか」「どう対策に活かすか」が命なんですよね。
だから、復習が雑になっていたり、時間が取れなかったりするなら、むしろ数は絞ったほうがいいんです。
それに、ご指摘のとおり、模試ばかりに気を取られて、学校のテスト対策が手薄になるのも避けたいところです。
通知表も受験に関わってきますから、定期テストは無視できないですよね。
「模試でボロボロでも通知表オール5!」みたいな人、あんまりいませんから。
とはいえ、模試をまったく受けないのも心配です。
じゃあ、どうするのがいいのか。
僕のおすすめは、「全部受ける前提じゃなくてもいいよ」というスタンスです。
たとえば、前半(春〜夏)は学力の伸びや弱点の発見が目的。
後半(秋〜冬)は志望校の判定を重視する、というように、役割を分けて考えてみるといいかもしれません。
そのうえで、1回1回の模試に「目的」を持たせて受けると、ただの“イベント消化”にはならないはずです。
「今回の模試は英語の文法を重点的にチェックしよう」とか、「国語の記述の得点アップが目標」みたいな小さなテーマを作ると、模試の意味がぐっと増します。
というわけで、「年6回は多すぎる?」という問いには、「全部をフル活用できるならアリ。でも、無理なら無理しなくてOK」というのが僕の考えです。
模試は、受けすぎると“点数に振り回されるレース”になってしまいがちです。
でも、上手に使えば“成績を上げるための道具”にもなります。
ぜひ、ご家庭のペースやお子さんの性格に合わせて、調整してみてくださいね。
そして、模試のたびに落ち込むことがあったら、こう言ってあげてください。「これは試合じゃなくて練習だよ」って。
それだけでも、ずいぶん気が楽になりますよ。
大石 基 先生
名張さかえ進学教室
私の塾では、県内の高校を志望している場合は塾内で年4回模試を実施しています。他府県の私立高校を志望している場合はそれ用の外部模試を受験していただきます。これは年2~3回です。受験者数の多い回を選んで受けてもらっています。
はじめのうちは結果よりも今後どのような学習が必要かを見るのが目的です。直前になると志望校判定を参考にします。判定はC以上だと可能性があると判断します。直前でD以下だと志望校の変更も検討することになります。ただ、模試の結果だけを見るのではなく普段の学習の様子からも判断します。しかし、客観性を齎すためには模試が必要です。
なお、模試を実施することによる塾の利益はほとんどありません。私の塾のように小規模な塾ですと赤字になることもあります。それでも実施しているのは進路指導に必要だからです。
山本 涼太郎 先生
個別教育クラーク
中学3年生の受験シーズンに入ると模試が増えるのは一般的ですが、親御さんとしては不安や負担を感じられるかもしれませんね。模試には以下のような目的があります。
◯現状把握と課題の明確化
模試を通じて、志望校の判定や学力の現状を把握し、どの分野を重点的に勉強するべきかを見極める材料にする。
◯客観的に実力を評価する
学校のテストとは異なり、全国規模での偏差値や順位を知ることができ、実力を客観的に把握する。
◯本番への慣れ
模試は試験本番を想定して作られているため、時間配分や緊張感への耐性を身につける練習機会とする。
ただし、ご指摘の通り、模試が増えることで学校のテスト対策がおろそかになるリスクもありますし、親子で精神的に疲れてしまうのも心配ですよね。そのため、以下のような工夫をしてみることをおすすめします。
◯模試の年間スケジュールを吟味する
年6回といっても、全てを受ける必要がない場合もあります。同時期に学校でも模試がある場合などは、最低限、必要なものだけに絞ることができないか、塾の先生に相談する。
◯模試の結果を長期的に見る
1回ごとの結果に一喜一憂するのではなく、数回分の結果を比較したり、受けたときの状況を分析したりして、成績の傾向を見るようにする。
◯学習計画のバランスをとる
模試対策と学校のテスト対策を並行するために、勉強の時間配分を計画的にすることが重要です。塾の先生に相談して、具体的なアドバイスをもらうのも一つの方法です。
息子さんにとって、模試が費用以上の価値を生むようサポートしつつ、親子で無理をしすぎない範囲で取り組むことが大切です。