高校生のオンラインの塾で親のサポートはどこまで必要ですか?
高校2年生の息子が部活と勉強を両立するためにオンライン塾を始めました。通塾の時間が減るのはありがたいのですが、正直、親としてどこまでサポートが必要なのか悩んでいます。授業の準備や進捗確認など、私が手を貸すべきなのか、それとも本人に任せて良いのかが分かりません。学校や部活のスケジュールも忙しいので、親の負担が大きくなるのではないかと心配です。オンライン塾は便利だと聞きますが、親が関わるべきポイントを知りたいです。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス
オンライン塾は生徒の自主性を育てる絶好の機会ですが、最初は保護者のサポートが重要です。具体的には、定期的な進捗確認と授業のスケジュール管理をサポートすることで学習習慣の定着を助けられます。一方で、すべてを親が管理するのは逆効果になる可能性もあります。学習内容についての直接的なサポートではなく、学習環境を整えることや相談に乗る程度の関わりが理想的です。月に一度、塾の講師と面談を行うことでも負担を軽減できます。
 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス
私自身も子どものオンライン塾をサポートしましたが保護者としては「見守り」が大事だと感じました。気をつけたことは、授業開始時間を一緒に確認したり、課題が終わったかを軽く声掛けするぐらいです。また、子どもが困った時に「どうしたらいい?」と聞いてくれる環境を作ることも重要です。ただ、過度な関与はお互いのストレスになります。家庭内で「自分でやってみる」というルールを決めると、親の負担も減って子ども自身の成長にもつながります。
 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス
オンライン塾に関して親が注目すべきは契約内容と安全性です。利用規約には退会や料金に関する条件が明記されているか、授業の遅延やシステム障害への対応がどうなっているかを確認しておきましょう。また、個人情報保護の観点で、生徒の学習記録やデータが安全に管理されているかも重要です。これらを事前に確認し、問題が発生した場合に迅速に対応できる準備を整えることで、保護者としての負担を減らせます。
本サービスで提供されるアドバイスや見解は、あくまで個人の意見です。これを参考にした結果生じた損害やトラブルについて、当社は責任を負いかねます。また、法的安心の視点でのアドバイスは正式な法律相談ではありません。具体的な法的問題は、専門の弁護士にご相談ください。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス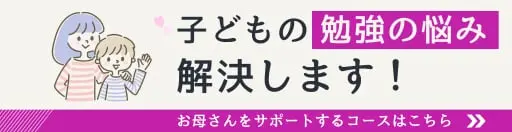
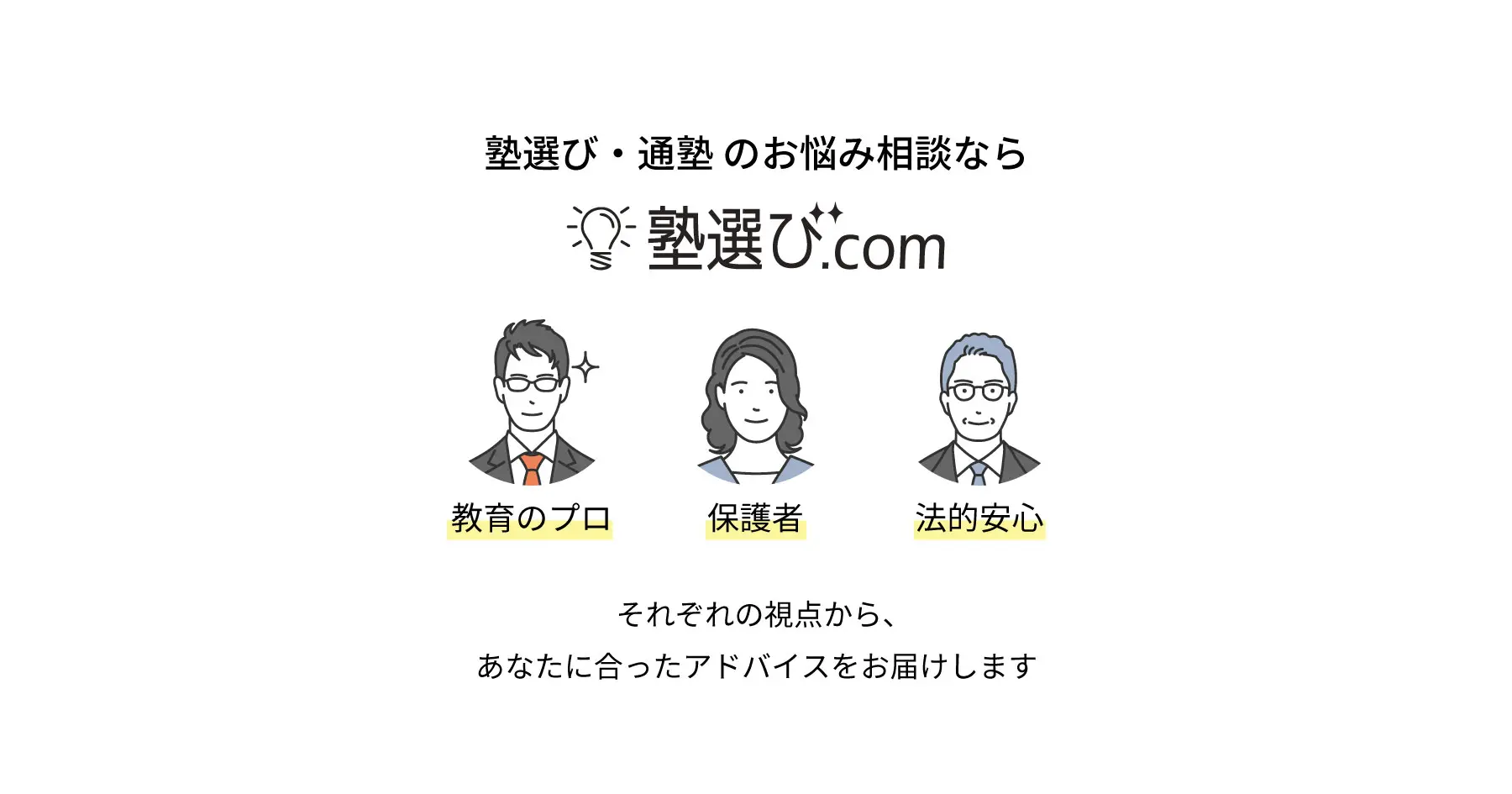


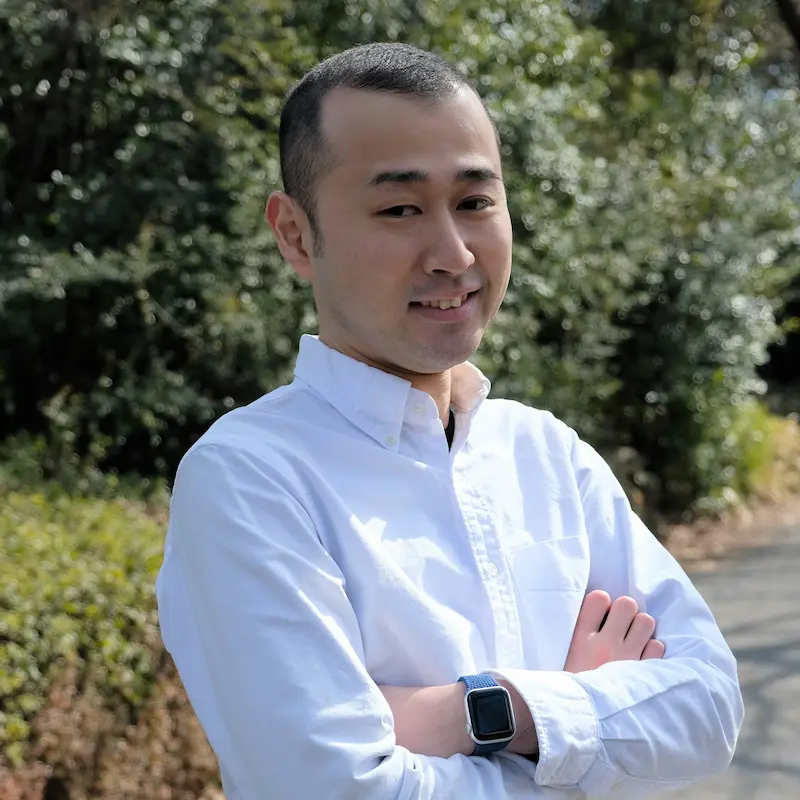






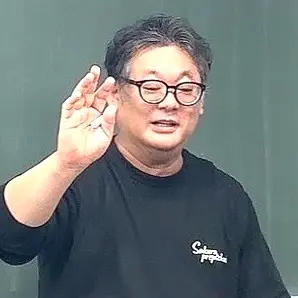



有識者の見解 (3件)
山本 力大 先生
オンライン個別指導塾Cheers!
高校生ともなると、勉強は自分の意思で取り組む「自学自習」が基本になります。
塾やオンライン学習はその手助けではありますが、最終的には本人が「なぜ勉強するのか」という根本的な部分を理解しているかどうかが大きな鍵です。
スケジュール管理や宿題の進捗を細かく見張るよりも、まずは「将来どうなりたいのか」「高校生活で何を大切にしたいのか」といった価値観の話をしてあげると、子ども自身のモチベーションが自然に芽生えやすいと感じます。
とはいえ、最初からすべてを子ども任せにしてしまうと、オンライン授業の時間を忘れてしまったり、トラブルが起きたとき対処できなくなる可能性もあります。
最初のうちは「機材やネット環境は大丈夫か」「今週はどの科目を重点的に学ぶのか」など、最低限のポイントだけ確認してあげるとよいでしょう。
ある程度慣れてきたら、親は一歩下がって見守り、様子がおかしいときにだけサポートを申し出るくらいが程よい距離感です。
また、部活と勉強の両立には「スケジュール管理」が不可欠ですが、それをすべて親が組んでしまうと子どもが依存してしまいます。
本人に考えさせたうえで、もし困っているようならアドバイスをしてあげると、自分で時間をコントロールする力も身に付きます。
大事なのは「がんばり方ややり方」は子どもの主体性に委ねながら、「どういう未来を目指したいのか」という根っこの問いを、親子で時々話し合ってみることです。
そうすると自然に本人の意欲が高まり、オンライン塾もただの受け身ではなく、主体的に使いこなせるようになっていくはずです。
高校生ともなれば、将来の進路を見据えるようになり、人から押し付けられた学習よりも「自分の意思」で選んだ勉強のほうがずっと力になります。
親の負担が大きくなるのを心配されるかもしれませんが、まずは息子さん自身にやらせてみて、必要なときだけサポートする。
そのスタンスで始めてみると、思いのほかスムーズにいくことも多いですよ。
根っこの話をしつつ、実務的なところはサッとサポートする。
そのバランスを探りながら見守ってあげてください。
子どもが「自分で決める」からこそ、本当の意味での成長につながると思います。
名川 祐人 先生
Studyコーデ
オンライン塾に通うのであれば、塾または担当講師と保護者がしっかりと連携体制を構築しておくことをお勧めします。
オンライン塾の弱点として、塾側から生徒の状況を細かく把握しづらいという点があります。
例えば私の所属するStudyコーデでは週3回の授業で、毎回小テストを実施して習熟度を把握し、週3回授業後に面談を実施して対話で状態の確認をしています。恐らくかなり丁寧に生徒とコミュニケーションをとっている塾です。
しかし、それでも生徒が「無断欠席」「未読スルー」という状態になってしまった場合、オンライン塾側からは何も状況把握ができなくなってしまいます。
そこで大切にしたいのが塾と保護者との連携です。
もし生徒と連絡が取れなくなったり、怪しい兆候があれば、塾から保護者に連絡をして、家庭での様子を聞き、対策を練ることが可能になります。
授業準備などの細かいことは家庭内で話し合ってスムーズな方法を見出してください。
オンライン塾でしっかり成績向上という成果を上げるために大切なことは、うまくいかなくなったときに、塾と家庭の双方から生徒を支援してあげられる体制をつくっておくことだと思います。
渡邉 靖子 先生
テラコヤイッキュー
高校生でしたら、お母さんのサポートは最小限にとどめてあげる方が良いですよ
塾の授業の準備なども自分の裁量で行うことで、勉強以外のちからが身に付きます。
そういった力は、大学生になってから・社会に出てから必要になってくるものです。
今のうちにお子さんに練習させてあげましょう!
きちんとできるか不安もあるかもしれませんが、
失敗することがあっても大丈夫です。失敗から学び、成長します。
お母さんが手伝ってあげると失敗はなくなるかもしれませんが、学びや成長の機会も少なくなってしまいます。
お母さんの関わるポイントは、
・頑張っている様子が見えたらしっかり褒めたり認める声掛けをしてあげる
・お休みや振替授業などの確認
・夏期講習や受験対策講座など、プラスアルファで必要になってくる講習の申し込み
・塾の先生との三者面談(あれば)
・ネット環境、お子さんが授業に集中できる環境の整備
くらいでしょうか。
一歩引いて、お子さんの成長につながるような関わりをしてあげてください