塾のSNSで見つけた心ない投稿、どう対処するべき?
先日、通っている塾のSNSアカウントで、うちの子を暗に指していると思われる投稿を見つけてしまいました。「やる気が見えない生徒がいる」「家庭の教育が行き届いていないのでは?」などといった内容で、名前は出ていないものの文脈からうちの子だとわかる内容でした。子どもは塾に対して不満はないため、こうした投稿を見たと知ればショックを受けると思います。直接塾長に伝えるべきなのか、それとも口コミサイトなどで匿名で注意喚起すべきなのか迷っています。塾を変えることも視野に入れていますがどう行動するのが最善なのでしょうか?
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス
まず、保護者として冷静に状況を把握することが重要です。その投稿が本当にお子さんを指しているのかを慎重に確認し、感情的な判断を避けましょう。その上で塾長に相談する際には「子どもが成長するにはどうしたらいいか教えてほしい」という前向きな姿勢を伝えることが効果的です。具体的には投稿の意図や背景について質問し、その内容が誤解を招く可能性があることを伝えるとよいでしょう。また、塾側にSNS運用の指針を見直すよう提案し、教育機関としての役割を再確認するきっかけをつくることが大切です。
 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス
保護者としてはまず、子どもの気持ちを第一に考えるべきです。子どもがSNS投稿を見ていないなら伝えるかどうかを慎重に検討しましょう。そして、直接塾長に話す際には「親として不安を感じている」という立場で伝えると相手も理解しやすくなります。匿名で口コミを書く前に対話の可能性を試みることをお勧めします。良識ある対応が子どもの環境を守る第一歩です。
 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス
SNSでの投稿内容が特定の個人を指していると感じた場合、名誉毀損やプライバシー侵害の可能性があります。まず、投稿内容のスクリーンショットを保存し、証拠として保管してください。その後、投稿者(塾長)に削除を求め、対応が得られない場合は法律相談窓口に相談するのも一案です。また、口コミサイトなどで注意喚起をする場合も具体的な事実を述べるにとどめ、感情的な表現は避けましょう。
本サービスで提供されるアドバイスや見解は、あくまで個人の意見です。これを参考にした結果生じた損害やトラブルについて、当社は責任を負いかねます。また、法的安心の視点でのアドバイスは正式な法律相談ではありません。具体的な法的問題は、専門の弁護士にご相談ください。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス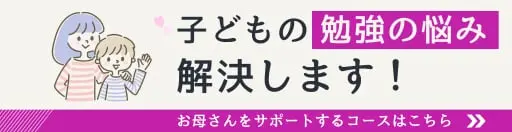
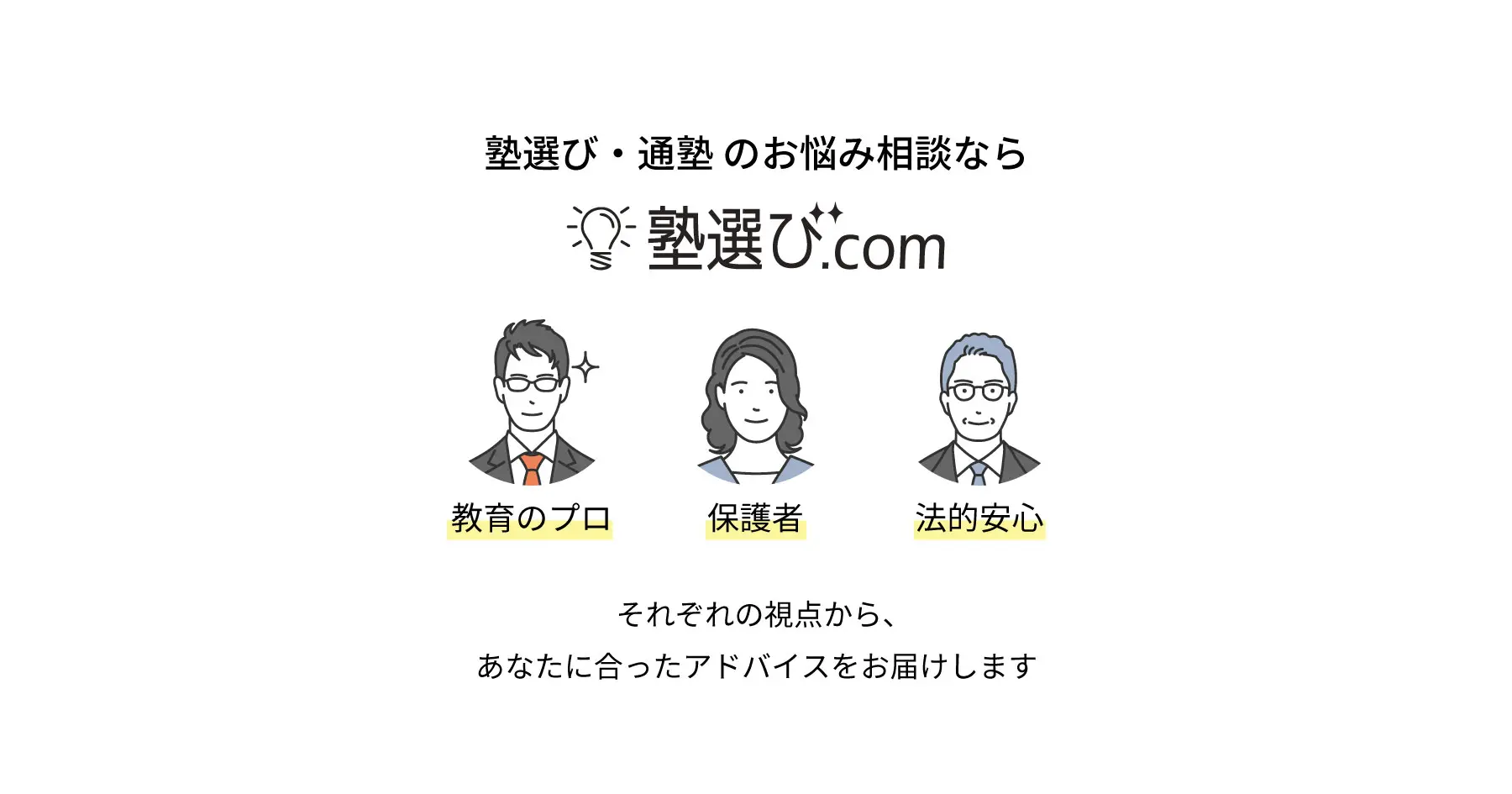


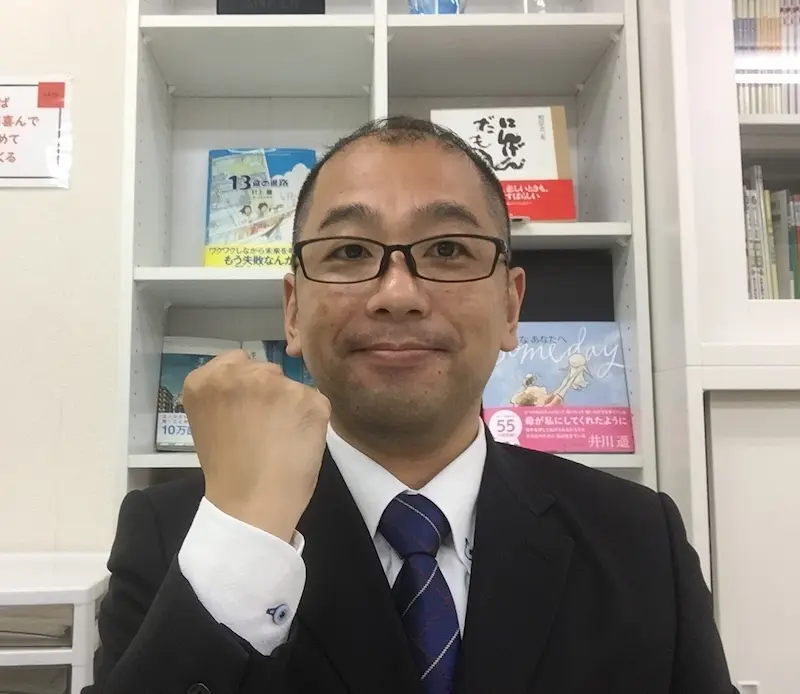





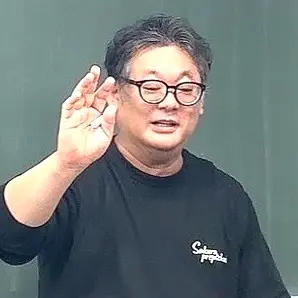



有識者の見解 (2件)
西尾 信章 先生
セルモ日進西小学校前教室
保護者様のお気持ち、そしてお子様の心情を考えると、大変つらい状況だと思います。信頼して通わせている塾からそのような投稿がされることは、不安や憤りを感じても無理はありませんね。まずは冷静に状況を整理し、慎重に行動することが大切です。
最初のステップとして、直接塾長に事実確認をすることをお勧めします。SNSの投稿内容がどのような意図で書かれたのか、またそれがご家庭やお子様を特定してのものなのかを明確に尋ねてみましょう。感情的に問い詰めるのではなく、あくまで冷静な姿勢で。
もし塾側の対応に納得がいかない場合や誠意が感じられない場合、他の選択肢を検討することも一つの方法です。塾を変えることを視野に入れる場合は、まずお子様と話し合い、新しい環境がストレスなく合うかどうかを優先して考えましょう。
最終的には、お子様が安心して学べる環境を整えることが最も大切です。保護者様の冷静な行動とお子様への寄り添いが、良い結果につながることを願っております。
沖津 亮佑 先生
個別進学塾セルフクリエイト水戸校
保護者様として、塾に対して不安や怒りを感じる内容ですね。
同じ学習塾を運営する者として、とても悲しく、申し訳なく思います。
お辛いかと思いますが、まずはその投稿のスクリーンショットを証拠として残しておきましょう。これは、塾を攻撃するためではなく、お子様を守るためです。
そして、塾長に直接、
「先日の投稿、うちの子のことではないと思うのですが、うちの子が見たらショックを受けそうなので、消していただくことはできませんか?」
のような問い合わせをすることが良いかと思います。
お子様に不安を与えないことを最優先に対応していきましょう。