塾長に不信感…でも子どもは先生を信頼している。どうしたらいい?
子どもを通わせている塾の塾長に対して不信感を抱いています。懇談のたびに言うことが変わったり、「前回と違う話をしていませんか?」と思うことが多く、本当に受験情報を理解しているのか頼りなく感じています。進路相談でも明確な指針がなく、「お子さん次第ですね」と言われるばかりで、親としては不安が募る一方です。でも子どもは担当の先生を信頼しているようで、子どもからは悪い話を一切聞きません。もっと信頼できる先生がいる塾に変えたい気持ちはあるのですが、子どもの気持ちを無視して塾を変えることはしたくありません。親としてどうしたらいいでしょうか?もうすぐ受験の学年になるので早めに決断したいです。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス
塾長の言動に一貫性がなく、受験情報に不安がある場合、直接的な進路相談は別の専門家に頼るのも手です。例えば、学校の進路指導や模試のデータを活用し、客観的な情報を補うことで、塾長のアドバイスに頼りすぎる必要がなくなります。また、お子さんが信頼する先生が指導を継続できるかどうかを確認し、可能なら教科指導はそのまま、進路相談のみ別の塾や家庭教師と併用する形を検討してみてください。お子さんの学習環境を維持しつつ、保護者の不安を解消する道を模索しましょう。
 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス
子どもが信頼している先生がいる以上、塾を変えることで学習意欲が下がる可能性が心配ですね。親としては、塾長の対応に不安を感じるのは当然ですが、まずはお子さんの気持ちをしっかり聞いてみましょう。「先生のどんなところが好き?」「塾でどんなことを学んでる?」と会話を重ねることで、お子さんの本音を探ることができます。その上で、塾長の発言が気になることを率直に塾側に相談し、他の先生に進路相談ができる環境があるか確認してみるのも一案です。どうしても不安が拭えない場合は、転塾の選択肢も含め、お子さんと一緒に納得できる形を探しましょう。
 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス
塾の契約内容を確認し、途中解約や変更の際のルールを把握しておくことは重要です。多くの塾では月謝制ですが、一部では違約金や解約手続きが複雑な場合もあります。また、塾の方針に疑問がある場合、消費者センターや教育関連の相談窓口に相談すると、第三者の視点で適切な対応策を提案してもらえることもあります。急に退塾を決めるのではなく、まずは事実を整理し、冷静に対応策を検討することが法的な安心につながります。
本サービスで提供されるアドバイスや見解は、あくまで個人の意見です。これを参考にした結果生じた損害やトラブルについて、当社は責任を負いかねます。また、法的安心の視点でのアドバイスは正式な法律相談ではありません。具体的な法的問題は、専門の弁護士にご相談ください。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス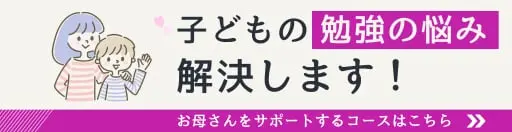
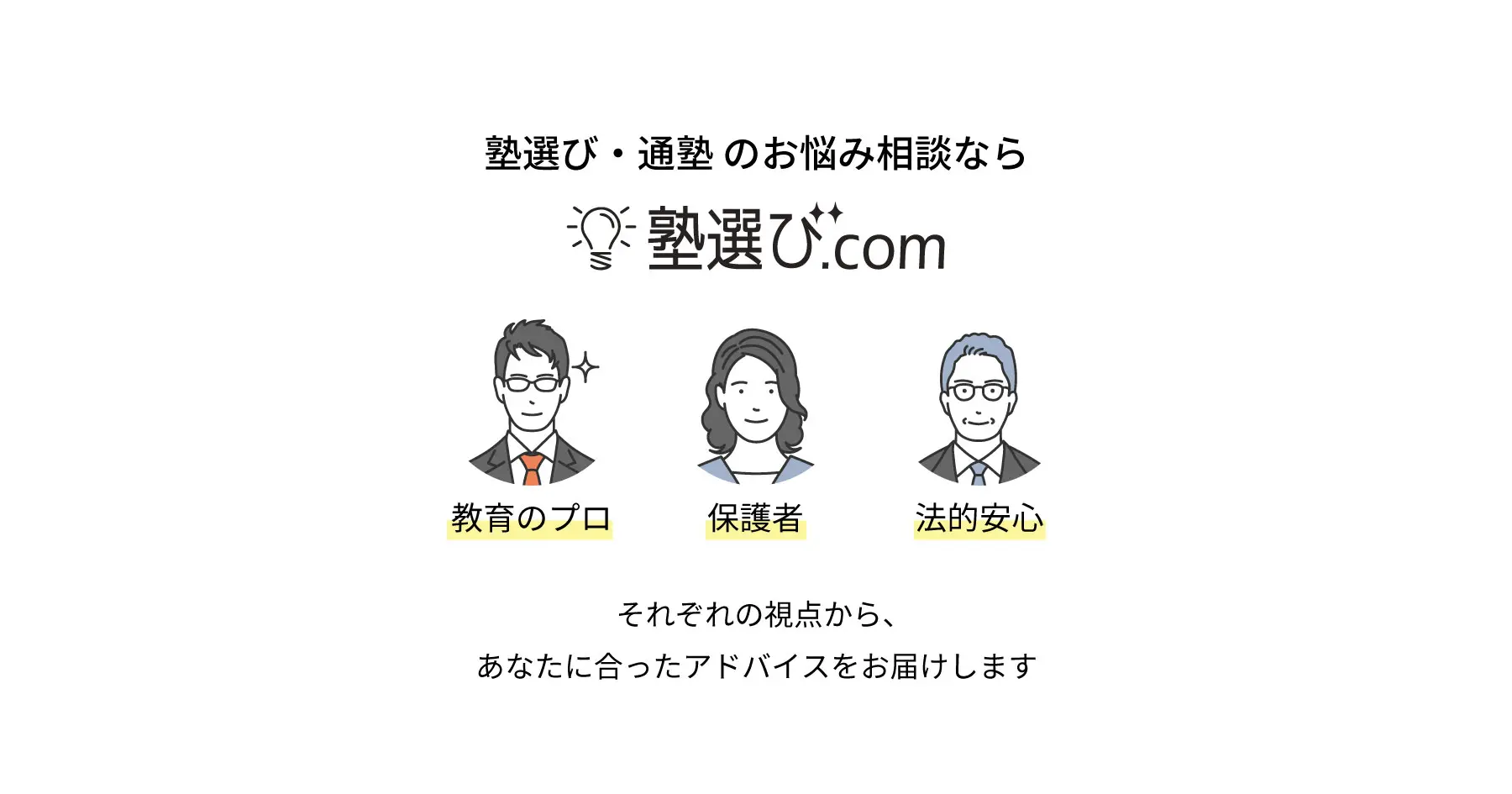

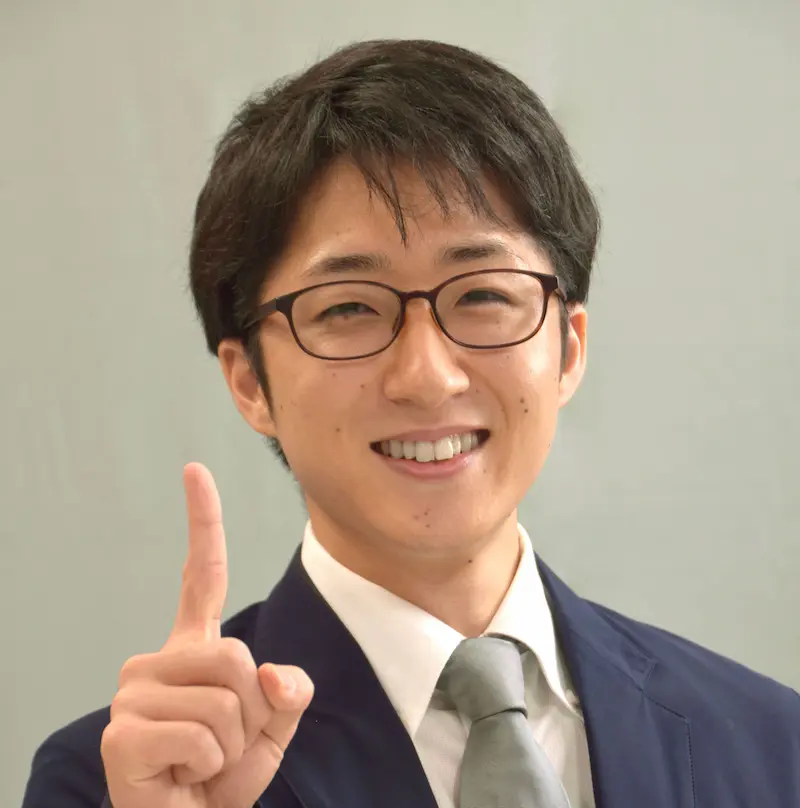






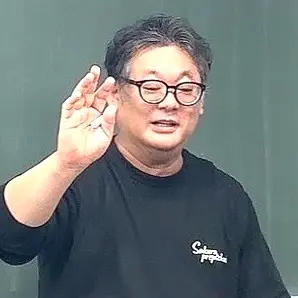



有識者の見解 (3件)
山本 力大 先生
オンライン個別指導塾Cheers!
こんにちは!
まず、保護者面談で言うことがコロコロ変わると、聞いている側はジェットコースターに乗っている気分になりますよね。進路の話は家の将来設計図でもあります。「お子さん次第ですね」で毎回締められたら、図面のないまま家を建てるようなものです。
一般的なアドバイスは二つあります。
ひとつは「塾長が微妙ならすぐ転塾」。もうひとつは「担当の先生を信じて続投」。どちらも真っすぐすぎるので、もう少し噛み砕いてみましょう。
鍵になるのは情報源の二層構造です。
上層(塾長)は受験データや学校説明会など“システムの情報”を管理する人。
下層(担当の先生)は日々の学習状況やメンタルを見守る“ヒューマン情報”の人。
今つまずいているのは上層だけ。下層は好調なら、この二層を切り離して考えると解像度が上がります。
そこで動き方を三段階に分けてみてください。
一 「データ面談」を別軸で設定する
次の懇談では、担当の先生も同席してもらい「今年の合格者データ」「昨年と比べた偏差値の推移」を印刷して持ってきてもらうよう事前にリクエストします。紙面があると発言のブレが減るうえに、その場で書き込みができるので後から確認もしやすいです。
二 第三者の“羅針盤”を一つだけ用意する
学校の進路指導部、教育相談センター、あるいは模試主催会社の個別相談会など、塾外の窓口で一度だけセカンドオピニオンを聞いてみましょう。塾長の話とズレがあるか、データで照らすと「何が曖昧か」がはっきりします。
三 子どもには「担当の先生を軸に学習を続ける」ことを伝える
大人が情報を精査している間も、子どもは目の前の勉強を進めたいはずです。「勉強は今の先生と続けて大丈夫。お父さんお母さんは進路データの部分だけ別ルートで確認しているよ」と共有しておくと、不安は最小限で済みます。
この三手で八月まで様子を見て、なおデータ面が頼りないままなら、秋以降に転塾か併塾(授業は残し、進路指導だけ別塾)を検討するのが現実的なタイムラインです。夏休みは学力を伸ばすゴールデンタイムなので、学習環境を大きく動かすのは避けたいところ。秋からの模試シーズンに合わせて舵を切り直すほうがリスクが低くなります。
というわけで
データは紙で確認
外部の羅針盤を一つ持つ
学習は担当の先生で継続
この流れで「情報の穴」を埋めれば、塾長さんとの温度差はダメージコントロールできるはずです。
西尾 信章 先生
セルモ日進西小学校前教室
塾長への不信感がある中で、お子さんはその塾の先生を信頼しているとなると、親としては悩ましいですね。とはいえ、大事なのは「お子さんが安心して学べる環境かどうか」です。お母さんが不安に感じていることを、まずは率直にお子さんに伝えた上で、お子さん自身はどう思っているのかを確認することが大切です。
もしお子さんが「今の塾がいい」と言うなら、少し様子を見てもよいかもしれません。ただ、塾長への不信が学習に影響しそうなら、具体的にどの点が気になるのか整理して、直接塾長に確認してみるのも一つの方法です。その対応によって、今後も任せられるかどうかの判断材料になりますよね。
また、転塾を考えるなら「お子さんが信頼できる先生がいる塾かどうか」も重要なポイントです。受験学年を迎える前に、複数の塾を見学し、お子さんとも相談しながらベストな選択をしていけるといいですね。最終的には、お子さんが「ここで頑張れる」と思える環境を整えてあげることが何より大切ですよ。
沖津 亮佑 先生
個別進学塾セルフクリエイト水戸校
塾長の発言が度々変わると、大きな不安を感じてしまいますよね。
特に、親子で塾への信頼度に差があると、なおさら戸惑われることと思います。
まずは、ご家庭で「受験に向けて塾をどう活用していくか」を話し合うことをおすすめします。
その際、親御様の考えを率直にお子様に伝え、お子様が担当の先生をどのように信頼しているのか、今の塾で受験まで頑張り続けられるのかを確認してみてください。
もしお子様が「今の塾で頑張りたい」と考えている場合は、親御様が感じている不安や疑問を具体的に塾へ伝えてみましょう。
例えば、以下のように質問すると、より明確な回答を得やすくなります。
「前回の懇談と今回の懇談で、異なる内容をお聞きしたように感じたのですが、改めてどのように進めるべきか教えていただけますか?」
「受験は子ども次第なのは承知していますが、親としてどのようなサポートをすればよいでしょうか?」
「○○高校を目指すと決めたのですが、受験対策はいつから本格的に始めればよいですか?」
直接質問するタイミングがない場合は、お電話やメールで確認するのもよいかもしれません。
親子ともに納得のいく受験が迎えられることを願っております。