勉強から逃げ続ける小5の子ども…どう向き合えばいいのか分かりません
小学校からは今の塾に行ってますが、勉強から逃げてます。
5年生ですが文章問題が得意ではなく、文章を読む事、本を読むことを避け、逃げてます。
本を読ませる習慣をつけてもすぐ飽きて続きません。
一日も欠かさず、勉強のことで母子が喧嘩をして早5年。
どうしたらいいか行き詰まっています。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス
文章問題が苦手な子は「読めない」のではなく「読みたくない理由」が隠れていることがあります。まずは正解させるより、読めた体験を積ませることを優先しましょう。問題文を親子で役割読みする、図解しながら読む、1行ごとに要点を色ペンで囲むなど、読む工程を分解して成功体験を作るのが効果的です。勉強=罰の構図を断ち切り、できた感触を積み上げることが再スタートの第一歩です。
 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス
私も同じように毎日バトルしていた時期がありましたが、ある日「勉強しなさい」をやめました。代わりに「今日は何分ならできそう?」と子どもに決めさせたら、意外と自分で動き始めました。やらされている状態だと逃げ続けますが、自分で決めたことは守ろうとします。まずは時間でもページ数でもいいので小さくても自分で決められる範囲を渡してみてください。親の役目は監督ではなく伴走者だと思えば、気持ちが少し楽になるかもしれません。
 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス
今回のケースは法的トラブルとは無関係に見えますが、親子喧嘩が慢性化している状態は精神的な負担が積み重なるリスクがあります。もし家庭内で勉強が原因の口論が増え、親子の関係が壊れそうな場合、学校や塾の先生、自治体の子育て相談窓口に早めに相談することも立派な対処です。保護者が追い詰められると、結果的に子どもも追い詰められます。家庭だけで抱え込まず、第三者を入れることは逃げではなく安全対策です。
本サービスで提供されるアドバイスや見解は、あくまで個人の意見です。これを参考にした結果生じた損害やトラブルについて、当社は責任を負いかねます。また、法的安心の視点でのアドバイスは正式な法律相談ではありません。具体的な法的問題は、専門の弁護士にご相談ください。
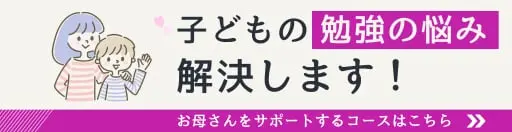
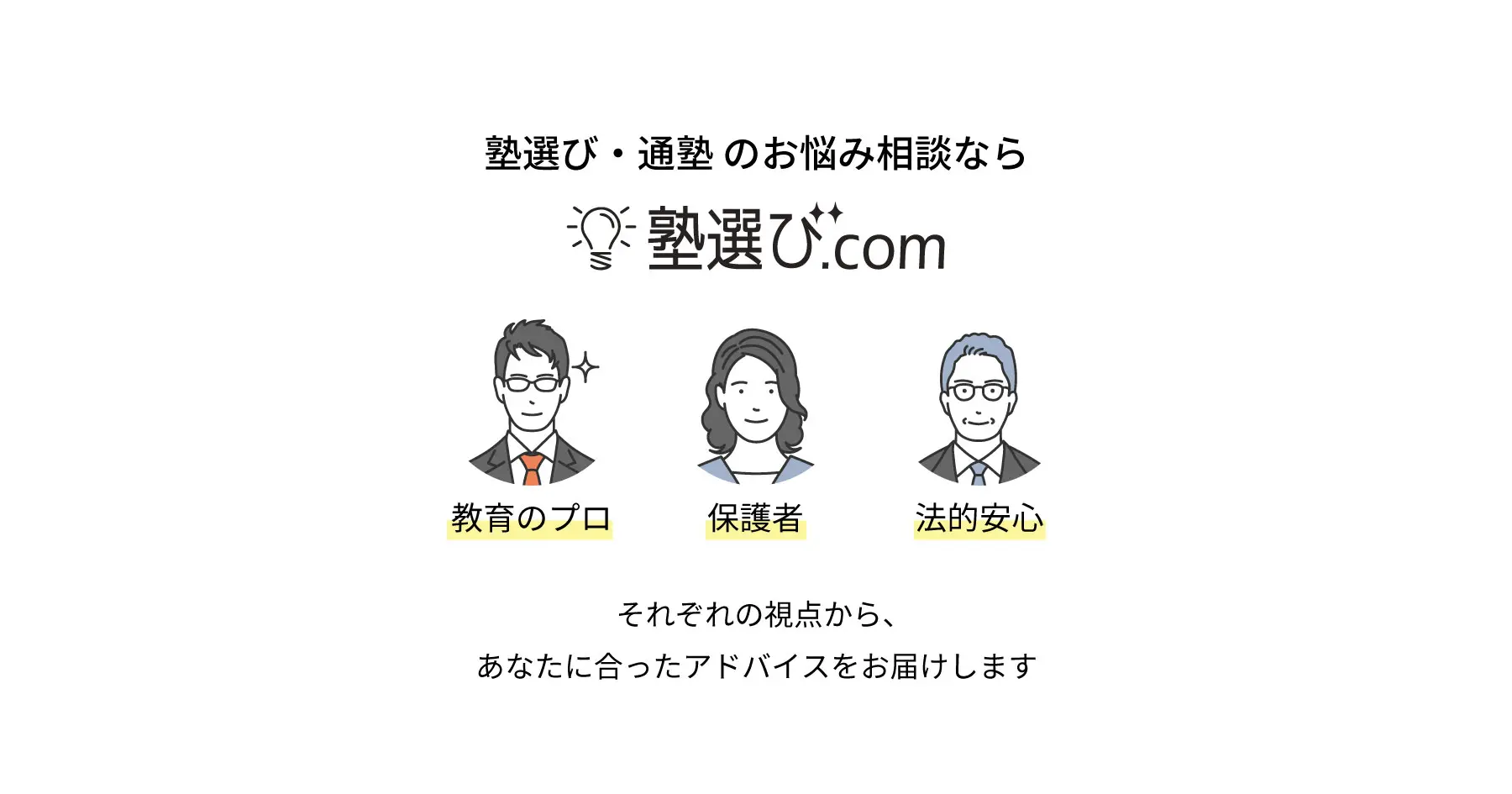









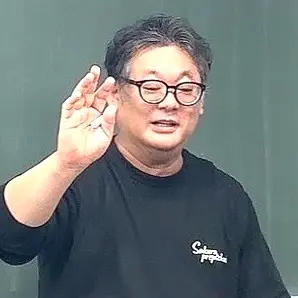



有識者の見解 (2件)
岡本 康志 先生
サポーツ京田辺
毎日欠かさず親子で喧嘩になり、お母様も大変お辛い状況だろうとお察しいたします。
お母様がまず、今、お子様は「逃げたいから逃げている」のではなく、「逃げざるを得ない状況に追い詰められている」という可能性について理解を深めていただくことが、状況を変える第一歩になるのではないでしょうか。
・ お子様の「逃げ」の背景にある可能性:人並み以上に辛い「読み書きの弱み」
お子様が文章を読むことや本を読むことを避け、勉強から逃げている背景には、単なる「やる気のなさ」ではなく、「読み書きの弱み」(発達の特性)が関わっている可能性があります。
1. 努力では埋まらない困難がある
読字の困難: 文章を読むこと自体が、お子様にとって人並み以上のエネルギーと集中力を要する作業になっているかもしれません。例えば、文字がぼやけて見える、行を読み飛ばしてしまう、文字を一つひとつ認識するのに時間がかかる、などが挙げられます。
「文章問題」が特に苦手な理由:
二重の負荷: 文章を「読む」という作業で既に疲弊するため、その内容を「理解し、思考し、問題を解く」という次の段階に進むための余力が残っていません。
読むスピードが遅い: 読むことに時間がかかり、周りの子と同じ時間で問題に取り組めないことで、強い劣等感や焦りを感じている可能性があります。
2. 辛い経験の積み重ねが「逃避」につながる
自己肯定感の低下: 小学校から5年間、努力しても周りと同じようにできない経験を重ね、「自分はできない子だ」という辛い思いを抱えてきた可能性が高いです。
精神的な防御反応としての「逃避」: 勉強を避けたり、飽きて続かないのは、「これ以上失敗して辛い思いをしたくない」「自分を否定されたくない」というお子様自身の心が、これ以上傷つかないための防衛本能かもしれません。
あえて お母様へ“向き合い方”として助言させていただくならば、
学習支援について教科書的には以下のようになります。
ステップ1:「できないこと」ではなく「辛さ」に焦点を当てる
お子様を責めたり、叱ったりするのを一度やめて、代わりに以下の言葉をかけてみてください。
共感と受容: 「文章を読むのはすごく大変なんだね」「頑張って読もうとしているのに、なかなか進まなくて辛かったね」
「戦う相手」を変える: 敵は「お子様」でも「お母様」でもなく、「お子様の読み書きを困難にしている何か」です。一緒にその「何か」と戦う姿勢を見せてください。
「どうしたらもっと楽に、文章が頭に入ってくるか、お母さんと一緒に工夫を探してみよう」
ステップ2:「読む」ことをサポートする工夫を取り入れる
もし読み書きに弱みがあるなら、根性論で「読ませる」のではなく、「読むことの負担を減らす」工夫が必要です。
音読の活用: お母様が読み聞かせる、または、教科書や本を読み上げてくれる音声教材(アプリや電子書籍など)**を活用し、「耳で聞く」ことで内容を理解するのを助けます。
視覚的な工夫: 読む行だけが見えるように**定規や穴あきの下敷き(リーディングトラッカー)**を使う、文字や行間を大きくしたコピーを使う、など視覚的な負担を減らします。
少しの成功体験を積み重ねる: 長文ではなく、短文の問題や、得意な科目、興味のあるテーマから始め、「できた!」という成功体験を増やして、自己肯定感を回復させてあげてください。
ステップ3:専門機関へ相談し、正確な状況を把握する
お子様の特性を理解し、適切なサポートを受けるために、専門家の力を借りることを強くおすすめします。
教育相談窓口: 学校の先生やスクールカウンセラー、地域の教育センターなどで相談し、学校での様子と家庭での困りごとを共有する。
医療機関: 必要に応じて、小児神経科、児童精神科、発達外来などを受診し、お子様がどのような特性を持っているのか(例:発達性読み書き障害、ディスレクシアなど)を正確に知ることが、最も有効な対策のスタートラインになります。
とはいえ、このような一般論的な助言を受けても、なかなかお母様としても実行が難しく感じられるでしょうし、現実的に【専門機関の専門家】という立場の方でも、この一般論程度しか理解されていないことがほとんどだと言っても過言ではないのが実情ですので、私としても、ここでの相談で終わらず、直接ご本人含めてお会いできればと、切に思います。(よろしければ、リモートでもご相談承ります)
ひとまず、今回のご助言としては、5年間も毎日、お子様と向き合い、お母さまご自身も悩みながら頑張ってこられたこと、「何とかしてあげたい」という強い気持ちの裏返しなのは間違いないでしょうから、お子様とぶつかるのではなく、二人三脚で共に問題を解決していくという方向でいかがでしょうか
田谷 智紀 先生
s-Liveきょうと山科校
お母さま、本当にお疲れさまです。
お子さんのために毎日向き合い続けてこられた、その姿勢は並大抵のものではありません。
文面から、深い愛情と、同時に「どうしてもうまくいかない」というもどかしさが伝わってきます。
おそらくお子さんは「勉強が嫌い」というよりも、
“お母さんと衝突するのがつらい”と感じているのかもしれません。
勉強=ケンカのきっかけ、となってしまうと、
本来前向きな学びの時間が「防衛の時間」になってしまいます。
また、お母さんご自身も「どう支えたらいいか」迷いながら、
それでも毎日声をかけ続けてこられたことでしょう。
これは心理学でいう“燃え尽き型の愛情疲労”の状態に近いかもしれません。
つまり、努力をしているのに報われず、自分の愛情さえ疑いたくなるほど疲れてしまう段階です。
ここで大切なのは、“頑張りをやめる”ことではなく、
「頑張る方向を変える」ことです。
勉強させるよりも、まず「お母さん自身の心を休ませる」こと。
安心した大人の姿こそが、子どもにとって一番の学びの環境になります。
たとえばこんな声かけがあります。
「今日は一緒にゆっくりしようか」
「やらない日があっても、あなたの頑張りは消えないよ」
こうした“責めない言葉”が、子どもにとって“安心の合図”にもなります。
もし家庭の中でこれ以上頑張るのが苦しいときは、
塾や第三者の先生に頼ることを恐れないでください。
外の大人が関わることで、親子の関係がいったん“リセット”され、
お母さんが「応援者」としての役割に戻ることができます。
子どもが変わるきっかけは、“親が信じて待つ勇気”の中から生まれます。
どうか一人で抱え込まず、ご自身の心も大切にしてあげてください。