面倒見の良さをアピールしてる塾ばかりで違いがわかりません
最近、塾を探し始めたのですが、どの塾もチラシやホームページに「面倒見が良い」「一人ひとりに寄り添います」といった言葉が並んでいて、正直どこも同じように見えてしまいます。面倒を見ることや寄り添うことは塾として当然の姿勢だと思うので実際に何が違うのかが分かりません。同じようなことが書かれている塾の見極め方が知りたいです。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス
「面倒見が良い」は抽象的な表現ですが、実際に差が出るのは仕組みです。たとえば、授業外フォローの具体性(質問対応の頻度・自習室の運営方針・面談の定期性)などを確認しましょう。塾によっては講師の裁量任せのところもあれば、マニュアル化されたサポート体制が整っている場合もあります。どう面倒を見るのかを数値や行動で説明できる塾ほど信頼できます。
 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス
正直、面倒見が良いと書かれていても、実際に面倒を見てくれるのはどこまでなのかが分かりにくいですよね。私は体験面談のとき、子どもが少し黙り込んだ瞬間に先生がどう反応するかを見ています。急かさず待ってくれるか、それとも話を進めてしまうか。その一瞬に寄り添う力が出ると思っています。子どもの表情が自然にほぐれる塾は、家庭での声かけも安心して任せられる印象です。
 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス
面倒見が良さをうたう塾でも、契約書に明記されていないサポート内容には注意が必要です。たとえば補習無料と言われても、回数制限や対象条件があるケースがあります。入塾前に書面での確認を忘れず、口頭説明だけで判断しないこと。トラブル防止のためにも、返金規定や休会・退会時の扱いを明確にした契約書を交わす塾を選ぶと安心です。
本サービスで提供されるアドバイスや見解は、あくまで個人の意見です。これを参考にした結果生じた損害やトラブルについて、当社は責任を負いかねます。また、法的安心の視点でのアドバイスは正式な法律相談ではありません。具体的な法的問題は、専門の弁護士にご相談ください。
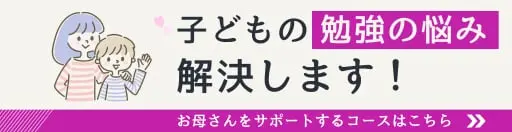
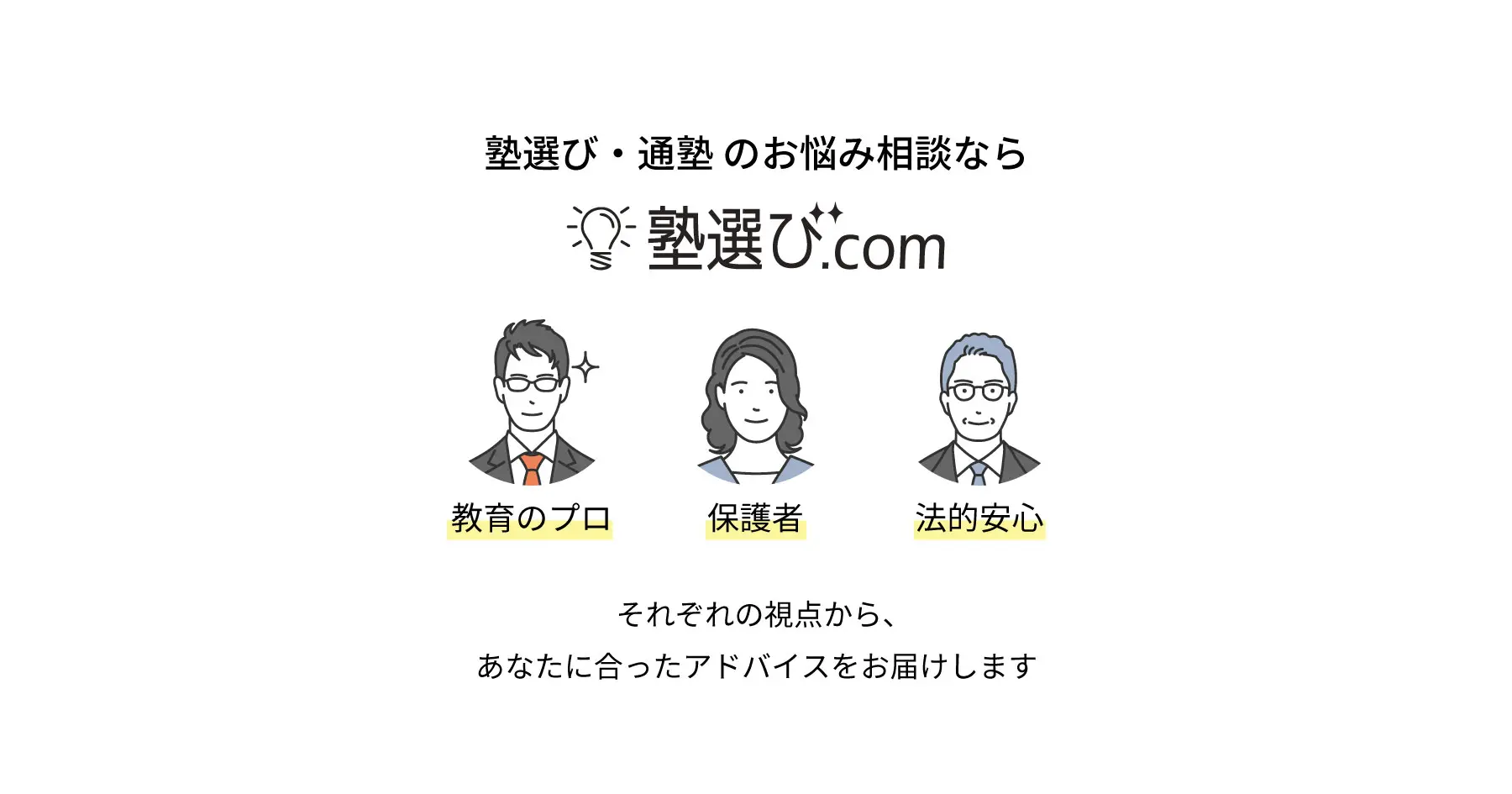

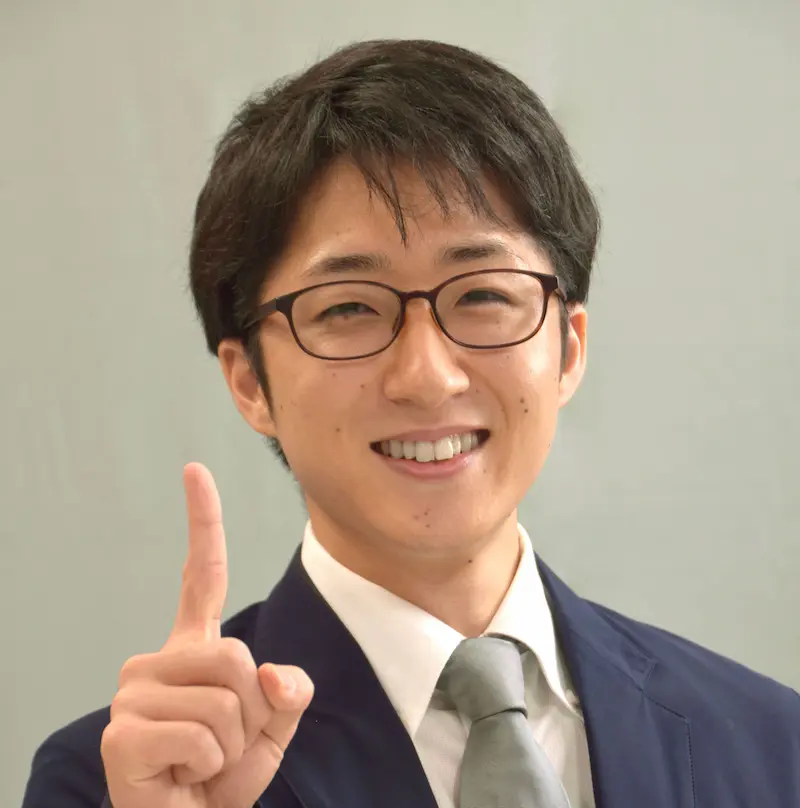





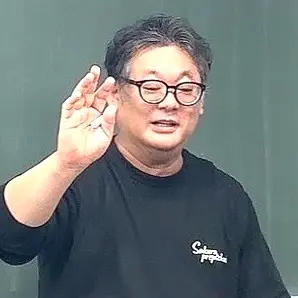



有識者の見解 (1件)
田谷 智紀 先生
s-Liveきょうと山科校
ご質問、とても本質的です。
今や多くの塾が「面倒見が良い」「一人ひとりに寄り添う」と掲げています。
確かに、文字だけを見ると違いが分かりません。
でも実際には、その“中身”や“実行の仕方”には大きな差があります。
では、何を見ればその違いを判断できるのでしょうか。
チラシやHPだけでは見えにくい“本当の中身”を見極めるための5つのポイントをご紹介します。
①【仕組み】寄り添いが“人の気持ち”ではなく“仕組み”として続くか
「面談はどのくらいの頻度でありますか?」「授業の様子は保護者に共有されますか?」
→ 寄り添いを継続できる仕組みがある塾ほど信頼できます。
“人による”ではなく、“仕組みで続く”かがポイントです。
②【時間】授業以外でどんなサポートをしているか
「テスト前や自習のときに、質問できる時間はありますか?」
→ “面倒見の良さ”は授業中ではなく、授業外でどれだけ支えてくれるかで分かります。
③【講師】講師が“子どもを見ているか”
体験授業のときに、「この子の得意・苦手はこうですね」と具体的に話してくれるか。
→ 教え方よりも、“観察してフィードバックしてくれるか”で講師の力量が見えます。
④【一貫性】誰が担当しても方針が同じか
「講師によって指導方針が変わることはありますか?」
→ 教室全体で理念が共有されていれば、担当が変わってもブレません。
個人任せの塾よりも、“チームで生徒を見る”体制がある塾を。
⑤【透明性】実績や保護者の声をどこまで開示しているか
「成績の変化や保護者の声はどんな形で見られますか?」
→ 成果・取組み・改善を数字や事例で見せられる塾は内部が整っています。
見せない=整っていない可能性もあります。
チラシの言葉は似ていても、塾の中身は“仕組み”と“姿勢”でまったく違います。
ぜひ体験や面談の際に、上記のような質問を投げかけてみてください。
回答の具体性・迷いのなさ・誠実さが、その塾の本質を映します。
最後にもうひとつ。
「面倒見が良い塾」とは、“手取り足取りやる塾”ではなく、“子どもが自分でできるようになるまで支える塾”です。
言葉よりも、行動でそれを感じられるか。そこを確かめてみてください。