志望校の過去問が難しすぎて、勉強の方向性に迷っています
高校生の娘が志望している大学の過去問に取り組み始めたのですが、あまりにも難しく自信を失ってしまいました。模試の結果では合格圏内に入る可能性があるのに、実際の過去問では解ける問題がほとんどなく、「私には無理」と言い出しています。塾の先生にも相談しましたが具体的な解決策が見つからず、親としてどのようにサポートすればいいのか困っています。過去問ができない段階で勉強の方向性をどう見直すべきか教えてください。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス
まずは、過去問を分析して解けなかった問題の種類やパターンを明確にしましょう。例えば、「基礎知識が不足している」「問題文の読解力が足りない」「特定の分野に偏っている」など原因を分けることが大切です。そのうえで、短期間で克服できる範囲を優先的に補強します。また、過去問を解く順序も重要です。いきなり最新年度の問題に取り組むのではなく、難易度が低めの年度から始めて成功体験を積ませることで、やる気を引き出しましょう。
 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス
お子さんが「無理」と感じているときは、まずその感情を受け入れて共感する姿勢が重要です。そして、過去問ができないのは「現時点での実力」であり、今後の努力次第で変えられることを伝えましょう。また、塾や家庭教師など専門家と一緒に具体的な学習計画を立てることで、不安を軽減する手助けができます。さらに、「勉強の過程を評価する」視点を持ち、お子さんが努力していることをしっかり認める声掛けを心掛けましょう。
 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス
塾側が十分なサポートを提供していないと感じるなら、契約内容やサービスの範囲を確認することも選択肢です。例えば、「個別の学習相談」や「過去問対策講座」が契約に含まれている場合、それを活用する権利があります。また、学習サポートに限界を感じる場合は、契約解除の規定や他の塾への転塾を視野に入れることも重要です。不明点があれば消費生活センターに相談し、適切なアドバイスを受けることも検討しましょう。
本サービスで提供されるアドバイスや見解は、あくまで個人の意見です。これを参考にした結果生じた損害やトラブルについて、当社は責任を負いかねます。また、法的安心の視点でのアドバイスは正式な法律相談ではありません。具体的な法的問題は、専門の弁護士にご相談ください。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス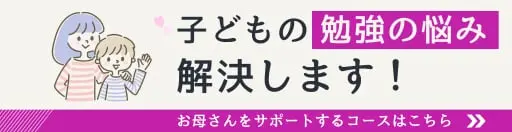
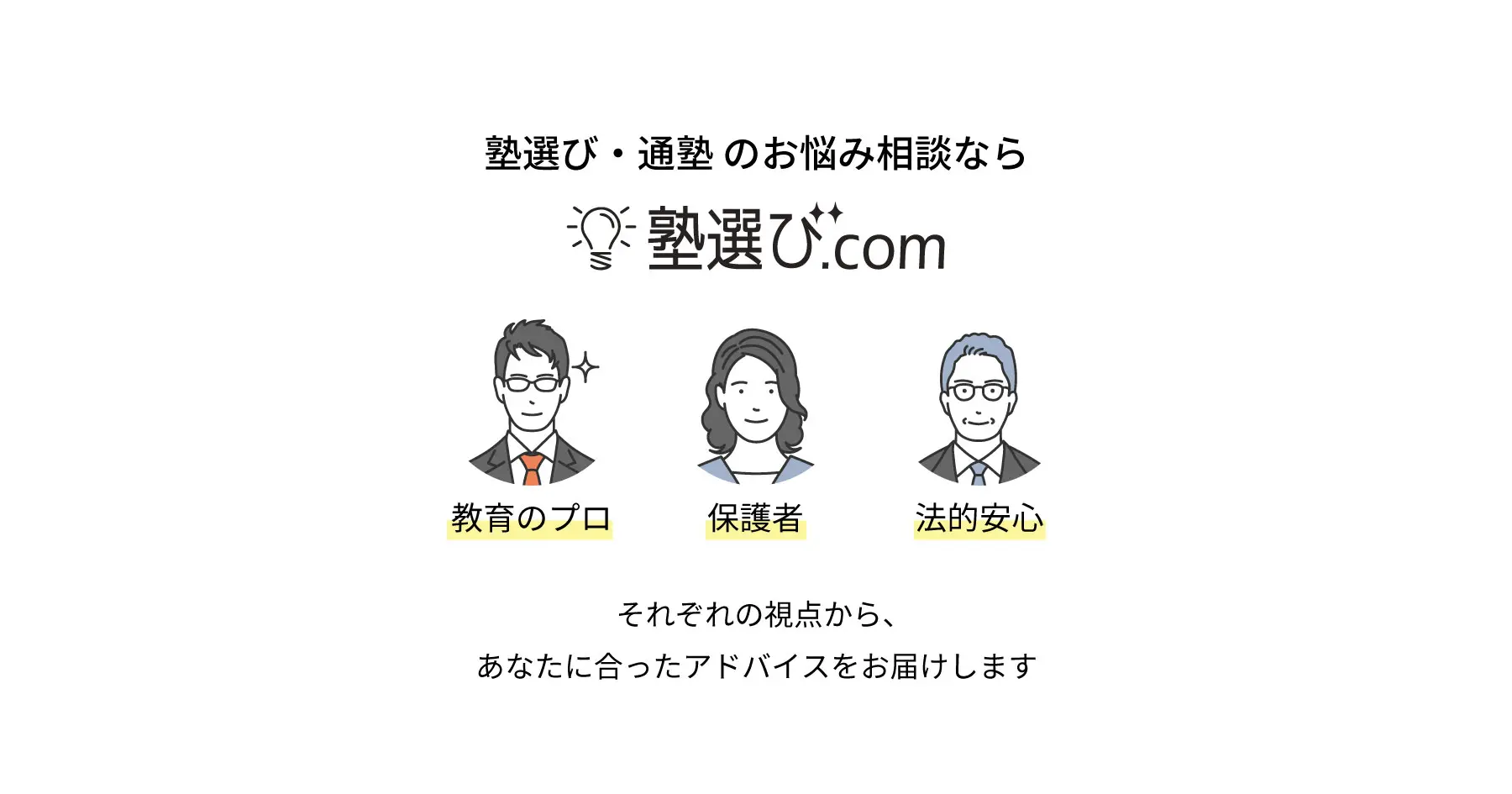
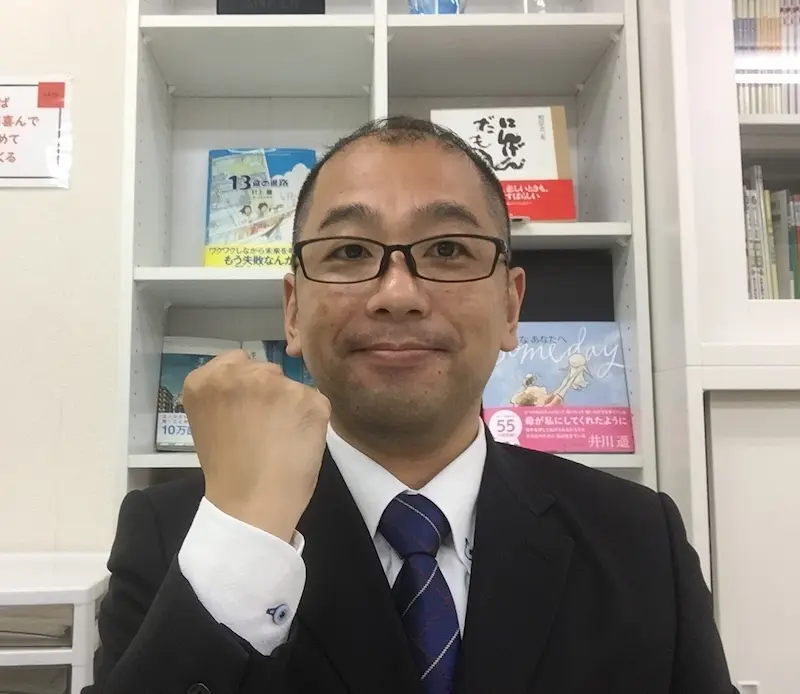

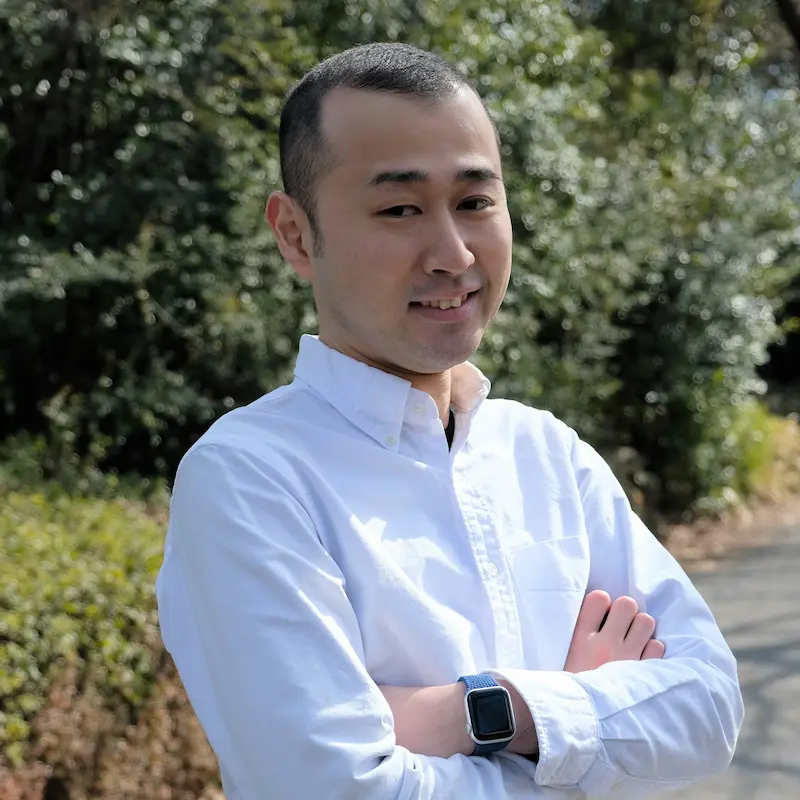





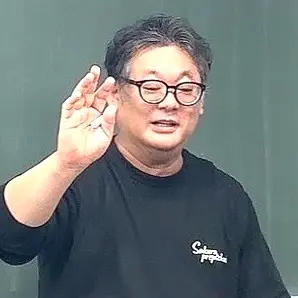



有識者の見解 (3件)
沖津 亮佑 先生
個別進学塾セルフクリエイト水戸校
模試の判定は良いけれど、過去問がなかなか解けないという高校生は少なくありません。
この場合、志望校が「私立」か「国公立」か、また模試が「マーク模試」か「記述模試」かによって、対応するべき方法が異なります。
それぞれのケースごとに、対策をお伝えいたします。
■ 私立 × マーク模試
共通テスト利用入試での合否判定が出されている場合、個別入試よりも共通テスト利用入試での受験をおすすめします。
共通テストの得点が重要になるため、まずは共通テストの過去問を中心に演習を重ねましょう。
■ 私立 × 記述模試
記述模試では、国公立の二次試験や私立の個別試験の平均的な問題が出題されます。そのため、「模試はできるけど過去問は解けない」ということが起こりやすいです。
まずは、なぜ過去問が解けないのか、その原因を明確にし、それを解消するための対策を進めましょう。
・記述問題の書き方がわからない場合
記述問題の対策を重点的に行い、先生に添削を依頼することが効果的です。
・知識不足で解けない場合
まずは併願校の過去問から取り組み、徐々に難易度を上げていきましょう。また、入試レベルの問題集を活用することも有効です。
■ 国公立 × マーク模試
国公立大学の場合、共通テストと二次試験の配点は大学ごとに異なります。
志望校の共通テストの配点が高い場合は、共通テストでより高得点を狙うことが重要です。そのため、共通テストの過去問演習を増やし、得点力を高めましょう。
さらに、合格に必要な総合点から逆算し、「共通テストで何点を目標にするか」「二次試験で何点を取ればよいか」の2つの目標を設定しましょう。この目標設定により、すべての過去問に取り組む必要がなくなるかもしれません。
■ 国公立 × 記述模試
国公立の二次試験の問題は、記述模試とは異なる傾向があります。そのため、模試の結果をそのまま二次試験の参考にするのは避けた方が良いでしょう。
対策としては、まず共通テストと二次試験のそれぞれの目標点を設定してください。
昨年までの合格者の平均点を参考に、目標点を具体的に決めましょう。
その上で、二次試験で必要な得点を確保するための具体的な学習計画を立て、効率的に進めていきましょう。
参考になれば幸いです。
中村 友 先生
高2までの英語塾OUTCOME
過去問が難しく感じるのであれば、一時的に過去問を解くことをやめて、解いた過去問の分析を徹底的に行いましょう。分析の観点としては以下です。
①まずは解説を熟読し、正解の根拠を正しく理解する
②問題の構成や制限時間、各設問の出題傾向を把握する
③不正解となった部分で、自分自身に現状なにが足りていないかを把握する
④次回過去問を解くときの方針の立案
過去問で最初から高得点が取れる生徒さんは滅多にいません。これらの分析を通して戦う相手を知り、対策を打つことができて初めて得点につながります。
お子さまはおそらく点数だけ見てしまって諦めているようにも思いますので、特に③でしっかりと振り返って、自分が足りないものを把握したうえで日々の勉強を進めていくことが重要だと考えます。
また、これまでの勉強のなかで「できるようになったこと」も一緒に振り返ってあげてください。模試で高得点が取れるようになったのは、お子さまがこれまで頑張ってきた証拠です。それがお子さまで実感できれば、過去問もこれからできるようになるかもしれないと前向きな気持ちになってくれると思います。
名川 祐人 先生
Studyコーデ
過去問に取り組むことを一旦止めて基礎力の向上に時間を使うか、少し難易度の低い大学の過去問に切り替えてみることをお勧めします。
過去問対策は開始時期がとても重要です。
一旦志望校のレベルを把握するうえで試しに解いてみる場合を除き、実力との乖離が大きい時期から過去問を解くことには、あまり良い効果がないと個人的には感じています。
本人にとってあまりに難しい問題を解いてしまうと「分からないことだらけ」「何が分からないか分からない」状態に陥ることがあります。これはモチベーションを下げるだけでなく、その演習からの学びが得られないことに繋がります。
本来過去問演習は、その演習を通して問題傾向を知り、その問題との戦い方や時間配分などを構想するなど、学びを得て次の演習に活かすことが目的であり、そのような経験を蓄積していくことで徐々に点数を上げていくことが可能になります。
また、その問題に正解するうえで自分にどんな力が足りていないのかを知り、そこを鍛え、また次の過去問に挑むという前向きかつ生産的なサイクルを創ることが理想です。
しかし分からないことだらけの状態では、自分の何を鍛えればいいのかもピンボケの状態となり、次に繋がる学びが得られにくい状況になってしまいます。
指導者によっては「高3の夏に赤本を10年分解くのが当たり前」などと言う人もいますが、人それぞれ開始すべきタイミングは違いますし、取り組むべき内容も異なります。周りの雰囲気や風説に惑わされず、その子に適した学習を見極めてあげることが大切です。