小学生の息子は多動症と診断されていて、じっと座っているのがとても苦手です。薬を使うことにはまだ抵抗があり、できれば本人の特性を理解し、温かく見守ってくれる塾を探してきました。でも実際には「ある程度集中できる子が前提です」と言われたり、「他の生徒への影響が心配」と遠回しに断られたりすることが多く、なかなか受け入れてくれる塾が見つかりません。親としては、勉強が好きな子の気持ちを応援してあげたいのですが、このまま通える塾が見つからなければ、やはり通塾はあきらめるしかないのでしょうか。
 教育のプロの視点からアドバイス
教育のプロの視点からアドバイス
 保護者の視点からアドバイス
保護者の視点からアドバイス
 法的安心の視点からアドバイス
法的安心の視点からアドバイス
本サービスで提供されるアドバイスや見解は、あくまで個人の意見です。これを参考にした結果生じた損害やトラブルについて、当社は責任を負いかねます。また、法的安心の視点でのアドバイスは正式な法律相談ではありません。具体的な法的問題は、専門の弁護士にご相談ください。
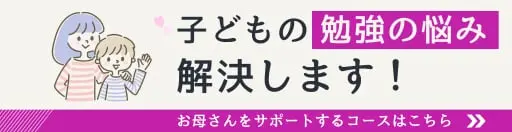
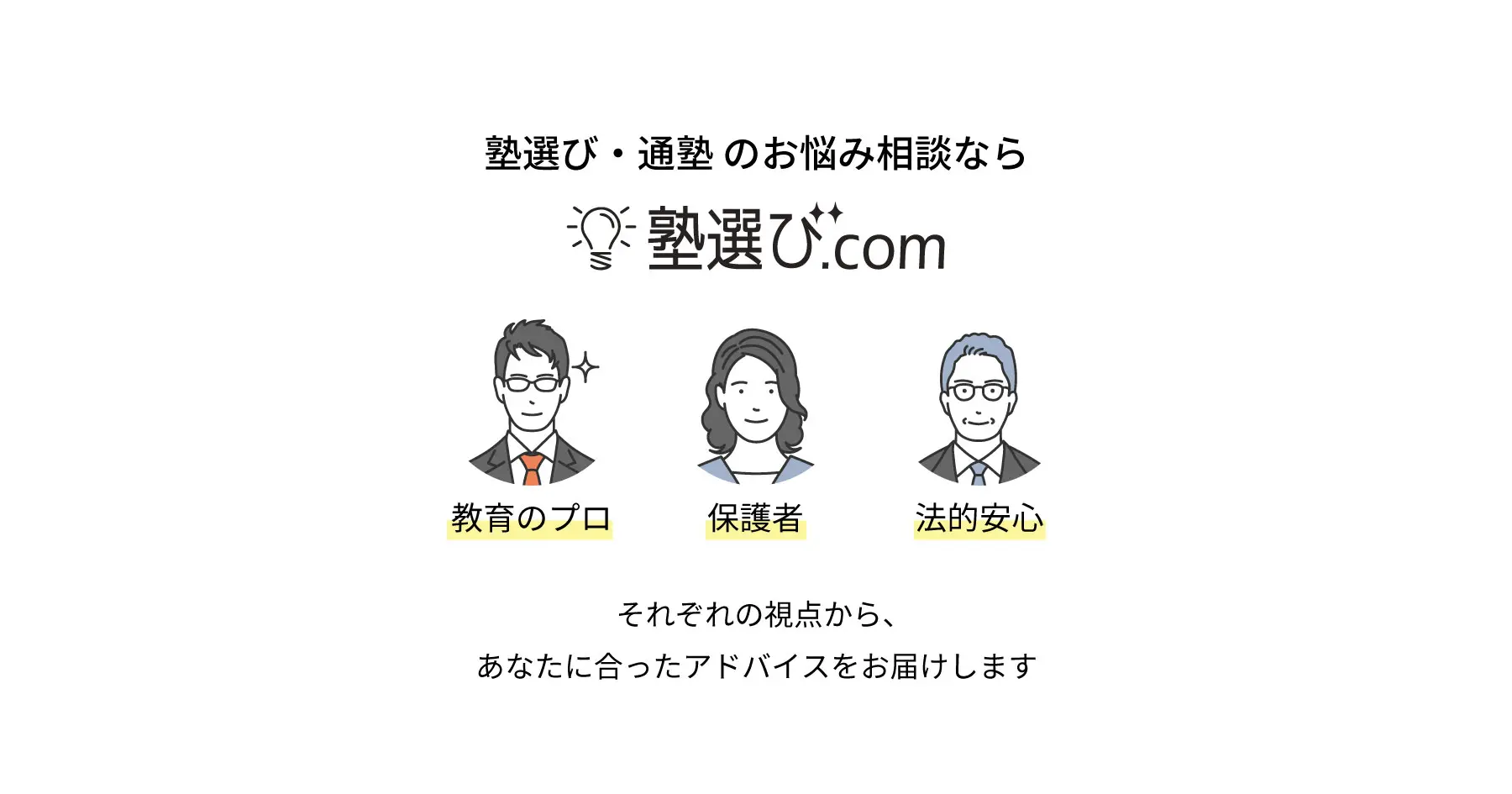









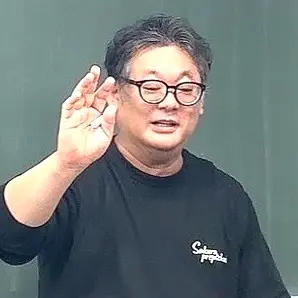



有識者の見解 (1件)
田谷 智紀 先生
s-Liveきょうと山科校
「このまま通える塾が見つからなければ、やはり通塾はあきらめるしかないのでしょうか?」
そう思ってしまうのは無理もないと思います。
でも、答えはNOと考えます。
もしかするとお子さんに原因があるわけではなく、
“特性を受け入れる準備ができている塾”がみつからないことが問題なのかもしれません。
◆受け入れ可能な塾を見つけるポイントを挙げてみました
1. 子どもへの対応が具体的か?
「集中が切れたときどう対応しますか?」
→「状況により臨機応変に」ではなく、具体的な工夫や実例を話せるかがポイント。
2. 「動く=ダメ」になっていないか?
立ち歩きや姿勢の変化があっても、学びを止めない工夫があるか。
叱るより“切り替えるサポート”を重視している塾が理想。
3. 教室の空気がどうか?
子ども同士の雰囲気、先生の口調、声かけのテンポ……
見学や体験でしか見えない“空気感”も、判断材料になります。
面談時での伝え方や質問も考えてみました
伝え方:
「学ぶことが好きで、本人なりの集中の形があります」
「興味のあることにはとても意欲的です」
→診断名や苦手なことばかりを先に話さなくてもOK。
質問例:
・「立ち歩いたりしたとき、どのように対応されますか?」
・「同じ教室に特性のあるお子さんがいた場合、先生はどう関わりますか?」
希望の伝え方:
NG:「注意しないでください」
OK:「失敗に敏感なので、声かけに工夫をいただけると安心します」
◆もし「なんか違う」と感じたら…
遠慮はいりません。
「合わないかも」と思った直感は、意外と的確です。
その場合は、無理に通わせず、視点を広げてみてください。
たとえば塾以外での 選択肢として
・オンライン個別/家庭教師
・フリースクールやNPO支援
・家庭学習+地域の居場所
もあるかもしれません。
学びの場は塾だけではありません。
大切なのは「通わせること」ではなく、“本人の意欲が続く環境”です。
お子さまは「じっとできない子」ではなく、「動きながら考える力を持った子」かもしれません。
その力を理解してくれる大人と出会えたとき、きっと学びはもっと楽しく、自由になるかもしれません。
焦らず、でもあきらめずに。
親としてその可能性を信じることが、いちばんの“学びの味方”と考えます。